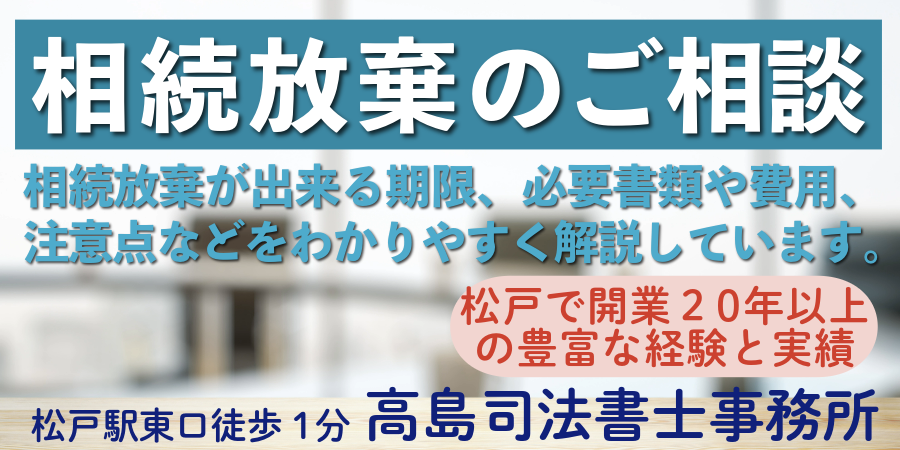相続放棄の申述
相続放棄のご相談なら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお任せください。
当事務所は2002年2月に松戸市で開業して以来、20年以上にわたり、相続放棄をはじめとする各種相続手続きについて、数多くのご相談・ご依頼を承ってきました。相続開始から3ヶ月を過ぎた後の相続放棄や、他の専門家から「これから相続放棄をするのは難しい」とされた事案についても豊富な取扱実績があります。
相続放棄に関するご相談は初回無料です。高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は予約制となっておりますので、ご来所の際は事前に「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご確認のうえ、ご連絡ください。
相続放棄の申述 目次
1.相続放棄とは?
3-1.手続きの流れ
3-2.必要書類
3-3.費用(裁判所費用、司法書士報酬)
4-1.相続放棄の熟慮期間の起算点
5-1.相続放棄は自分でも出来るのか
5-2.相続人が未成年である場合の相続放棄(特別代理人の要否)
5-4.相続放棄申述受理証明書の交付申請
1.相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなられた方(「被相続人」といいます)の一切の財産を承継しないために、法定相続人が家庭裁判所に対して行う手続です。
相続の対象となる財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産(資産)だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産(債務・負債)も含まれます。相続人となるのは成人だけではなく、未成年者であっても同様にすべての財産を承継することになります。
そのため、被相続人に多額の借金があり、遺産を処分しても返済が難しいような場合には、相続放棄を選択することで、これらの債務を相続しないことが可能です。相続放棄をした相続人は、法律上「初めから相続人でなかったもの」とみなされ、債務の支払い義務を負うことはありません。
相続放棄を行うには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
司法書士に相続放棄の申述手続を依頼すれば、申立書類の作成だけでなく、家庭裁判所への提出代行、さらに必要に応じた債権者への通知などを一括して任せることができ、松戸市周辺で相続放棄を検討している方にとって非常に有用な手続サポートが可能です。
相続放棄は期限が決まっている手続きです。亡くなられたご家族に多くの債務があり、相続放棄が必要だと思われる場合には、早急に司法書士までご相談ください。松戸で相続放棄のご相談なら高島司法書士事務所へどうぞ。
2.相続放棄の申述(家庭裁判所)
相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。相続人同士で、誰が遺産(資産・負債)を承継するかについて合意したとしても、その合意のみでは、被相続人に対する債権者からの請求を拒むことはできません。
たとえば、被相続人の財産および負債のすべてを長男が承継する旨を、法定相続人(配偶者および長男以外の子)が全員で取り決めたとしても、それだけでは長男以外の相続人も、被相続人の債務について弁済義務を免れることはできません。
被相続人の債務を承継しないためには、家庭裁判所で相続放棄の申述を行い、これが受理されることが不可欠です。家庭裁判所により申述が受理されて初めて、法律上「相続を放棄した」ものとして効力が生じます。
3.相続放棄申述の手続き
ここでは、家庭裁判所における相続放棄申述の流れについて説明します。なお、司法書士へご依頼いただく場合には、相続放棄申述書その他の提出書類の作成から家庭裁判所への申立てまで一括して対応いたしますので、難しい作業をご自身で行う必要はありません。
3-1.手続きの流れ
(1) 相続放棄の申述
相続放棄を行うには、被相続人の最後の住所地(相続開始地)を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書および戸籍謄本等の添付書類、必要な収入印紙・郵便切手を提出します。
家庭裁判所への書類提出は司法書士が行いますので、ご依頼者様が家庭裁判所へ出向く必要は原則としてありません。
(2) 文書による照会
相続放棄申述書等を提出後、一定期間が経過すると、家庭裁判所から「照会書」が送付されます。これは、相続放棄の意思が真意によるものか、また手続が適切に行われているかを確認するためのものです。
とくに、被相続人の死亡から3ヶ月を経過した後の申述の場合には、事情説明が必要となることがあります。しかし、司法書士に依頼されている場合には、申立時に事情説明書を添付していますのでご心配いただく必要はありません。
照会書の回答内容そのもので受理・不受理が左右される可能性は高くありませんが、質問内容を正確に理解せず誤った記載をすると、手続に支障が生じる場合があります。照会書が届きましたら、速やかに司法書士へご連絡いただき、回答内容の確認を受けてから返送してください。
(3) 相続放棄申述受理の通知
相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。これにより、相続放棄が正式に認められたことが確認できます。
必要に応じて、「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることも可能です。債権者への提出、相続登記を行うときなど、各種手続きで相続放棄したことの証明書が必要となる場合に取得します。
3-2.相続放棄申述の必要書類
家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う際に、最低限必要となる書類は次のとおりです。
- 相続放棄申述書 1通
- 申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本 1通
- 被相続人の除籍(戸籍)謄本および住民票の除票 各1通
被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)や兄弟姉妹が相続放棄をする場合には、その方が相続人であることを証明する必要があるため、さらに多くの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍等)の取得が必要となります。
これらの戸籍収集は一般の方にとって手間も負担も大きく、内容の判断も難しい場合があります。当事務所にご依頼いただければ、必要となる戸籍類はすべて司法書士が代わりに取得いたしますので、安心してお任せください。
3-3.相続放棄申述の費用
(1) 家庭裁判所の費用(実費)
相続放棄申述には、申述人1名につき収入印紙800円と、照会書等の郵送用としての切手(110円切手を数枚分など)が必要です。これらは家庭裁判所へ提出します。
(2) 司法書士の費用(報酬)
当事務所へ相続放棄申述をご依頼いただく場合、司法書士費用は次のとおりです。
- 相続人1名の場合:基本報酬 44,000円
- 相続人2名以降:1名につき 基本報酬 22,000円を加算
相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月が経過しており、事情説明書(上申書)等の作成が必要となる場合には、追加費用(11,000円~)が発生することがあります。その際は、ご依頼前に必ずお見積りをご提示いたしますのでご安心ください。
また、当事務所で戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や住民票等を取得する場合には、1通あたり1,100円の手数料と実費がかかります。
(3) 費用についてのご注意
他の司法書士事務所では、「相続放棄者1名あたり〇円」といった料金体系を採用していることがありますが、相続人の人数が多い場合には総額が想定以上に高額になるケースもありますので注意が必要です。
当事務所では、2名目以降は基本報酬を半額とすることで、費用負担の増加をできる限り抑えています。
たとえば、被相続人の子、その直系尊属、兄弟姉妹と続けて相続放棄の手続を進める場合でも、2人目以降はすべて基本報酬の半額となります。
なお、兄弟姉妹が相続人となる場合など、一部の事務所では通常より高額な設定がされていることもあるようです。依頼前に、司法書士報酬の総額がいくらになるのかを必ず確認することをお勧めします。
4.相続放棄できる期間
4-1.相続放棄の熟慮期間の起算点
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります。この熟慮期間がいつから開始するかについては、以下のように判断されます。
まず、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因となる事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となった事実を知った時をいいます。
(1) 相続開始の原因となるべき事実とは
「相続開始の原因となるべき事実」とは、被相続人が死亡した事実を指します。したがって、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合には、その事実を知った時から3か月以内が熟慮期間となります。この場合、被相続人の死亡から長期間が経過していたとしても、死亡の事実を知った時から3か月以内であれば相続放棄は可能です。
ただし、このようなケースで相続放棄の申述を行う際には、「なぜ死亡を知らなかったのか」について、家庭裁判所に対し詳細な事情説明が求められます。手続にあたっては、必ず専門家に相談されることを推奨します。
(2) 自分が相続人となった事実
自分が相続人となった事実を知った時点が問題となるのは、第2順位(直系尊属)または第3順位(兄弟姉妹・その代襲相続人)の相続人が相続放棄をする場合です。被相続人の配偶者や子(または代襲相続人)は、相続開始と同時に相続人となり、その事実も同時に認識します。
これに対し、先順位相続人が存在する場合、第2順位以下の相続人は相続開始時点では相続人ではありません。しかし、先順位相続人が相続放棄をした時点で、はじめて相続人となります。つまり、先順位相続人が相続放棄した事実を知った時が、「自分が相続人となった事実を知った時」に該当します。
したがって、先順位相続人の相続放棄を知った時から3か月以内であれば、相続放棄の申述を行うことが可能です。
4-2.特別な事情がある場合の熟慮期間の起算点
相続放棄(または限定承認)は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内(熟慮期間)に行わなければならず、この期間を経過すると単純承認したものとみなされます。単純承認とは、相続人が被相続人の財産も負債もすべて承継することを意味します。
しかし、特別な事情がある場合には、被相続人が死亡した事実および自分が相続人となった事実を知った時から3か月を過ぎていても、相続放棄が認められる余地があります。
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は『相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時』から起算すべきものである(最高裁判所 第二小法廷 昭和59年4月27日判決)。
上記の最高裁判決からすると、たとえば「被相続人が亡くなったことは知っていたが、長期間疎遠で財産状況を把握することが困難であった」「借金の存在を認識していなかったことについて、やむを得ない事情があった」などの場合には、相続財産の存在を認識した時点から熟慮期間を起算できる可能性があります。
さらに、現在の家庭裁判所の実務では、「相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白な場合に限り、申述を却下する」との取扱いが通常です。
当事務所が取り扱った事例においても、相続財産の一部を認識していたケースであっても、相続放棄が受理された例は多数存在します。しかし、正確な法的知識や実務経験が不足している専門家に相談した結果、「今からの相続放棄は不可能です」と誤って断言されてしまう事例も少なくありません。
相続開始から3か月を経過した後の相続放棄は、専門的な判断と実務経験が不可欠です。申立実績が豊富な専門家に相談することを強くお勧めします。3ヶ月経過後の相続放棄でお困りの方は、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
5.相続放棄のよくある質問
5-1.相続放棄は自分でも出来るのか
相続開始から3ヶ月以内で、かつ特別な事情が存在しない一般的な相続放棄の手続であれば、裁判所ウェブサイトから申立書式を入手するなどして、ご自身で手続きを進めることも不可能ではありません(裁判所「相続の放棄の申述」ページはこちら)。
ただし、相続放棄の申述は一度却下されてしまうと、同じ相続について再度の申立てを行うことはできません。したがって、「まずは自分でやってみて、うまくいかなければ専門家に相談する」という方法は、取り返しがつかなくなる可能性があるため避けるべきです。
また、申述後には家庭裁判所から照会書(質問書)が送付されますが、その内容は申立てをしてみるまで分かりません。質問の趣旨を誤解して回答した場合、手続に支障を生じる可能性もあります。最後まで責任をもって対応できる場合を除き、専門家に依頼することを推奨します。
さらに、
- 相続開始から3ヶ月を経過してしまった場合
- 相続財産の処分行為に該当するおそれがある場合
- 相続債務の存在を後から知った場合
などは、熟慮期間の判断や事情説明が特に重要となるため、相続放棄手続に精通した専門家へ相談すべきです。松戸の高島司法書士事務所は「相続放棄の相談室」サイトも運営し、相続放棄に関する豊富な取扱実績を有しております。専門性の高い案件についても安心してご相談ください。
5-2.相続人が未成年である場合(特別代理人の要否)
相続人が未成年である場合には、法定代理人である親権者(父・母)が未成年者に代わって相続放棄の申述を行います。ただし、親権者と未成年者との間に利害の対立(利益相反)が生じるときは、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があります。
特別代理人の選任が必要となる具体的なケースは次のとおりです。いずれも親権者が未成年者を代理すると、未成年者に不利益が生じる恐れがある場合です。そこで、第三者である特別代理人が未成年者の利益を保護する必要があります。もし、これらの場面で特別代理人の選任が不要とされれば、親権者が未成年者にのみ相続放棄をさせ、遺産を独占することさえ可能になってしまいます。
特別代理人の選任が必要となる主な例
- 未成年者と法定代理人(親権者)が共同相続人であって、未成年者のみが相続放棄申述をする場合(親権者が先に相続放棄をしている場合を除く)。
- 複数の未成年者の法定代理人(親権者)が、一部の未成年者のみを代理して相続放棄申述をする場合。
未成年者と法定代理人との利益が相反する場合が問題なのですから、たとえば、親権者が相続放棄申述をした後に、未成年者全員を代理して相続放棄申述をする場合、また、親権者と未成年全員が同時に相続放棄申述をする場合には特別代理人選任は不要です。
5-3.相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会
ある相続人(または相続人であった人)が相続放棄の申述をしているかについては、家庭裁判所へ照会することで確認できます。
また、相続放棄をしていること自体は分かっているものの、相続放棄申述の事件番号や受理年月日が不明な場合であっても、「相続放棄等の申述の有無についての照会」を行うことで、事件番号および受理年月日を把握することが可能です。
たとえば、先順位の相続人が存在する場合、その人が相続放棄をしていれば、次順位の人が相続人となります。しかし、先順位相続人に直接確認することが難しいケースも少なくありません。このような場合であっても、家庭裁判所に照会することで、当該相続放棄・限定承認の申述の有無を確認できます。
ただし、照会の申請が出来るのは、下記に該当する方に限られます。
- 相続人(照会者自身が相続放棄・限定承認の申述をしたか否かは問いません)
- 被相続人に対する利害関係人(債権者等)
5-4.相続放棄申述受理証明書の交付申請
相続放棄申述受理証明書が必要な場合には、家庭裁判所へ交付申請を行います。たとえば、不動産の相続登記(名義変更)を行う際、他の相続人が相続放棄している事実を証明するために、受理証明書の提出を求められることがあります。
相続放棄申述受理証明書の交付申請は、通常、相続放棄の申述と同時に申述人が行いますが、申述人本人以外の利害関係人(共同相続人、被相続人の債権者等)による申請も可能です。その場合には、相続放棄者との利害関係を示す資料の提出が必要となり、家庭裁判所が相当と認めたときに限り証明書が交付されます。
もっとも、共同相続人からの申請については、申請人の戸籍謄本の提出程度で足り、それ以上の資料は求められないのが通常です。
また、交付申請書には、相続放棄者の氏名のほか、相続放棄申述の事件番号および受理年月日の記載が必要です。これらが不明な場合には、まず「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を行い、事件番号および受理年月日を確認することになります。
6.まとめ(相続放棄は松戸の高島司法書士事務所へ)
相続放棄は、家庭裁判所への申述という専門性の高い法的手続きであり、誤った判断や不十分な事情説明によって却下されてしまうと、二度目の申立はできません。とくに、相続開始から3ヶ月を過ぎてからの相続放棄は、熟慮期間の判断や特別な事情の立証など、専門的な知見と豊富な実務経験が不可欠です。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市・松戸駅徒歩1分)は、相続放棄の相談・申立書類の作成・戸籍収集・事情説明書の作成まで一括サポートしており、開業以来20年以上にわたり、松戸市内はもちろん、千葉県・東京都・埼玉県・茨城県など広域から多数のご依頼をいただいております。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市・松戸駅徒歩1分)は、相続放棄の相談・申立書類の作成・戸籍収集・事情説明書の作成まで一括サポートしており、開業以来20年以上にわたり、松戸市内はもちろん、千葉県・東京都・埼玉県・茨城県など広域から多数のご依頼をいただいております。
- 相続放棄を考えている
- 相続開始から3ヶ月以上経ってしまった
- 債権者から突然通知が届いた
- 他の専門家に「これからの相続放棄は無理」と言われてしまった
こうしたケースでは、ぜひ一度当事務所にご相談ください。相続放棄は一度きりの重要な手続きです。松戸の地元密着の司法書士事務所として、皆さまの状況に寄り添い、確実に手続きが完了するよう全力でサポートいたします。
関連情報
松戸の高島司法書士事務所にご相談ください
遺産相続に関連する手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は完全予約制なので、電話でご予約いただくか、または、ご相談予約・お問い合わせページのメールフォームをご利用ください。
当事務所へお越しいただいてのご相談は初回無料で承っています(当事務所へ依頼する予定は無く相談のみをご希望される場合には、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も承っておりません)。相続放棄のことなら松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)へご相談ください。
お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら
TEL: 0120-022-918
電話受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、いつでもご遠慮なくお電話ください。なお、平日は18時過ぎまで電話がつながることが多いです。